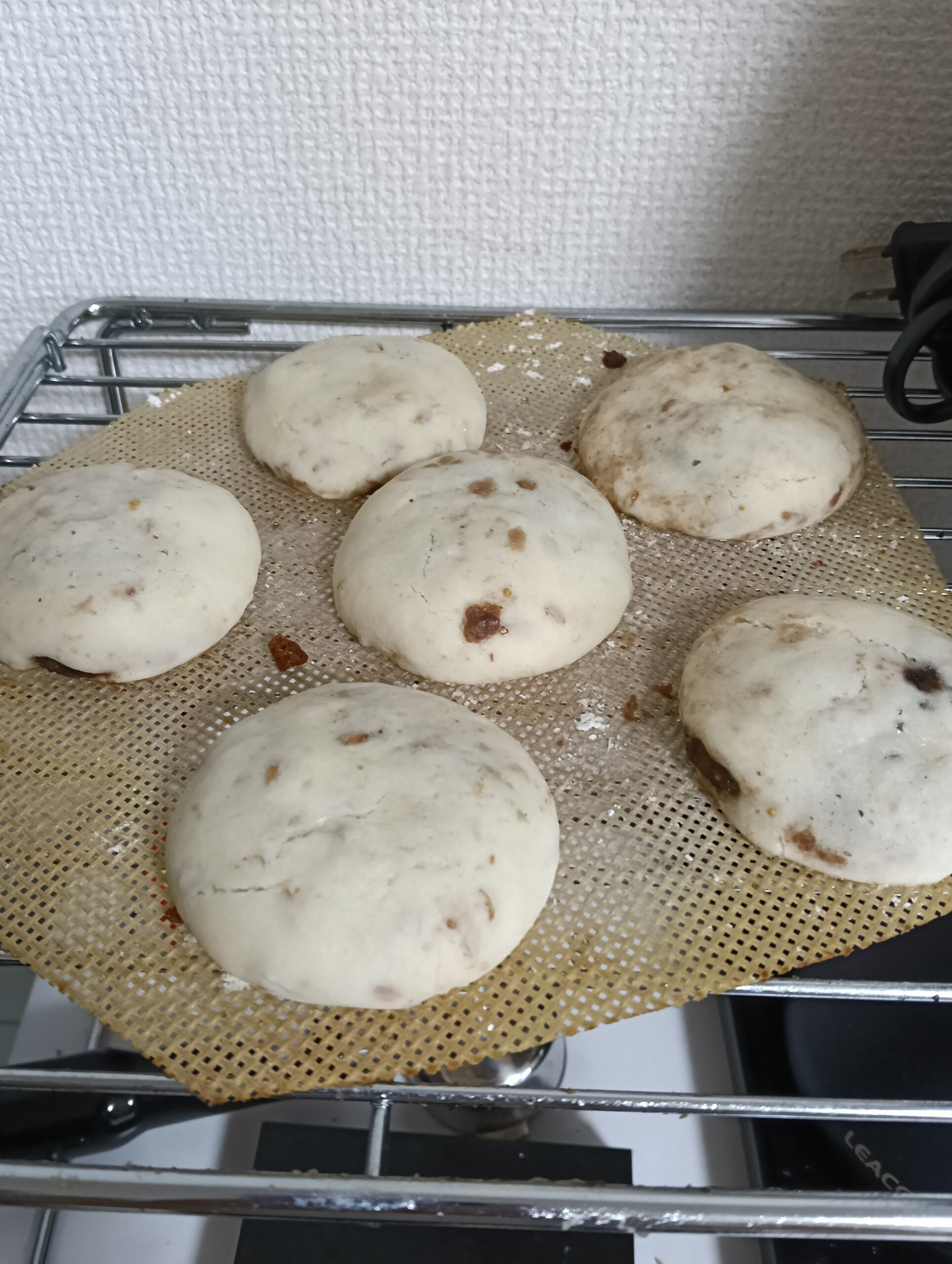ヴィーガンとしての日常栄養素編~ビタミン~
前回、前々回に引き続き、ヴィーガンとしての一日の栄養事情について紹介していきたいと思います。
最後はビタミン。ビタミンは人間が体内で合成できないものも多く、できたとしても不十分な場合も多いため、食物からの摂取が重要となります。
基本的に緑黄色野菜や果物に多く含まれているため、ヴィーガンなら大分余裕で摂取できるのでは?とわたしも思っておりましたが、ビタミンB群などは結構意識しないと不足しがちです。
三大栄養素やミネラルは、豆類や穀物、海藻で十分賄えることを考えると、最も摂取難易度が高いのはこのビタミンなのかもしれません。
各種ビタミンの摂取事情
ビタミンA(レチノール活性当量)
- にんじん(119.5㎍/16.6g)×2回
- 小松菜(45.8㎍/20g)×2回
- トマト(45㎍/100g)
- ブロッコリー(49.6㎍/65g)
- 葉ネギ(30㎍/25g≒1本)×2回
- 大根(29.2㎍/10g)×2回
- パプリカ(26.4㎍/30g)
- 三つ葉(24.5㎍/10g)×2回
- 海苔(23㎍/1g≒3分の1枚)×2回
- ひじき(13.9㎍/乾燥5g)
- オクラ(6.9㎍/16g≒3分の4本)×3回
- レタス(5㎍/25g≒1枚)
- ほか
一日の摂取量:708㎍以上
摂取難易度:★★★★☆
最初は脂溶性ビタミンの一種で、βカロテンとかレチノールとかの総称であるビタミンA。ビタミンAは皮膚や粘膜を正常に保つ美容ビタミンとも呼ばれているようです。厚生労働省のデータベースではレチノール活性当量という項目が、指標となっております。こちら、にんじんに非常に多く含まれていることで有名ですね。一応わたしは人参をひじき煮とあんかけに使っているからその辺で多く摂れたりします。勿論人参に完全に依存するわけにもいかないから他の食材からもとりますが、特に多く含まれているのは、小松菜、トマト、ブロッコリー、葉ネギといった緑黄色野菜のお馴染みのメンツに加え、味噌汁の具材の最大手(当社比)大根にも結構な量が含まれています。なお、脂溶性ビタミンは他にもビタミンD、ビタミンE(αトコフェロール)、ビタミンKがありますが、これらは摂りすぎると体内に蓄積され、過剰摂取の副作用リスクがあるので、摂取量は多すぎても少なすぎてもダメになります。そういう意味では、推奨量700㎍近くなのでバランスがいいのではないかと思っております。
ビタミンD
- きくらげ(4.4㎍/乾燥5g)
- まいたけ(2.8㎍/50g)
一日の摂取量:7.2㎍
摂取難易度:★★★★★
続いてはビタミンD。カルシウム、リンの吸収促進の働きがあり、人間が日光を浴びることで生成されるものでもあります。が、ヴィーガンにおいてはビタミンB12と並んで最も摂取難易度が高いビタミンだと思います。理由は簡単で、植物性食材から摂取できる手段が、上に上げた舞茸、きくらげ以外にはほとんどないと言ってもいいからです。キノコ類ならばほかにもいくつかありますが、摂取できる分量はあまり多くないため、必然的に上記2種に頼りがち。一応干ししいたけならば、1株あたり0.4㎍くらいあるのでそちらもありかもしれません。椎茸は他のキノコに比べて少し高額なので、家計と相談かもしれませんが。また、ビタミンDは脂溶性ビタミンゆえ、油で炒めると摂取効率が上がるのだとか。舞茸やきくらげは炒め物にするのがよさそうですね。
ビタミンE(α-トコフェロール)
- アーモンド(2.8mg/10g)
- ブロッコリー(2.2mg/65g)
- パプリカ(1.3mg/30g)
- ゴールドキウイ(1.0mg/40g≒2分の1個)
- トマト(0.9mg/100g≒2分の1個)
- オリーブオイル(0.7mg/9g)
- ひよこ豆(0.6mg/乾燥16g)
- ほか
一日の摂取量:9.5mg以上
摂取難易度:★★☆☆☆
お次は若返りビタミンとも呼ばれているビタミンE。昨今ではアーモンドミルクの知名度上昇に伴い注目度も上がっているビタミンですね。
そのアーモンドに多量に含まれているのは勿論、様々な栄養素を多く含むブロッコリーにも多めに含まれています。カリウムが豊富なことで知られるトマトにも結構含まれているみたいですね。疲れた時にはトマトをかじるのもいいのかもしれません。
サラダに適した野菜に多く含まれているし、ドレッシングにも適しているオリーブオイルにも多めに含まれているので、疲れた夜や起きがけの朝にサラダを食べるのは、ビタミンE豊富という意味で理に適っているのかもしれません。
ビタミンK
ビタミンKは、ビタミンK1とK2の2種類があるようなのですが、特に重要なのはK2の方で、これは必要量自体は納豆1パックで一日に必要な量はあっさり満たせます。逆を言えば納豆を食べ過ぎたら脂溶性ビタミンゆえに蓄積されて過剰摂取となりかねないので、これが納豆は一日多くても2パック位にしとくべき、ってことなのかもしれません。働きとしては、骨や血液の凝固に必要な栄養素で、カルシウムの流出を抑制することで、骨がもろくなるのを防ぐのに重要な働きを持つらしいです。そのため、不足すると骨粗しょう症リスクなどが高まるんだとか。納豆以外にはブロッコリーなどにも多く含まれます。
ビタミンB1
- 木綿豆腐(0.16mg/2分の1丁)
- オートミール(0.06mg/30g)
- ひよこ豆(0.06mg/乾燥16g)
- 納豆(0.05mg/1パック≒40g)×2回
- トマト(0.05mg/100g≒2分の1個)
- ブロッコリー(0.04mg/65g)
- 豆乳(0.03mg/100ml)
- ごはん(0.03mg/150g)×2回
- 十六穀(0.02mg/6g)×2回
- 里芋(0.03mg/50g)×2回
- パプリカ(0.02mg/30g)
- 葉ネギ(0.02mg/25g≒1本)×2回
- オクラ(0.01mg/16g≒3分の4本)×3回
- にんじん(0.02mg/33g)
- 米粉パン(0.02mg/52.5g)
- りんご(0.01mg/62.5g≒4分の1個)
- レタス(0.01mg/25g≒1枚)
- 舞茸(0.04mg/50g)
- くろごま(0.01mg/1g)
- 小松菜(0.01mg/20g)×2回
- ゴールドキウイ(0.01mg/40g≒2分の1個)
- のり(0.01mg/3分の1枚)×2回
- ごぼう(0.01mg/20g)×2回
- ほか
一日の摂取量:0.91mg以上
摂取難易度:★★★★★
ここからは水溶性ビタミンになります。ビタミンB群の一つ、ビタミンB1。疲労回復ビタミンともいわれており、糖質をエネルギーに変換するための補酵素の一つであるため、効率よくエネルギーを補給するのには欠かせないビタミンです。が、その摂取難易度の高さもかなりのもの。見ての通り、特定の食材に豊富に含まれている、というのがほとんどありません。かろうじて万能食豆腐くらいで、それ以外は一食当たりだと0.1mgすら入っていない始末。なので、様々な食材をバランスよく、多岐にわたって摂るしかありません。偏った食生活でなくいろいろな食材をバランスよくとりましょう、と言われるゆえんの一つには、こういった特定の食材に依拠できない栄養素があるからかもしれないなあと思った次第です。こうしてみるとご飯と納豆の組み合わせは、ごはんから糖質を、納豆からビタミンB1を摂ることでエネルギー変換効率を上げるという栄養学的観点からも優秀な組み合わせなのが見えてきますね。
ビタミンB2
- 納豆(0.12mg/40g≒1パック)×2回
- アーモンド(0.1mg/10g)
- 木綿豆腐(0.07mg/2分の1丁)
- ブロッコリー(0.0815mg/65g)
- パプリカ(0.045mg/30g)
- 葉ネギ(0.0275mg/25g≒1本)×2回
- 昆布だし(0.045mg/200ml+250ml)
- オートミール(0.024mg/30g)
- ひよこ豆(0.024mg/乾燥16g)
- 海苔(0.023mg/1g≒3分の1枚)
- まいたけ(0.07mg/50g)
- 豆乳(0.02mg/100ml)
- トマト(0.02mg/100g≒2分の1個)
- 豆味噌(0.018mg/15g)×2回
- しょうゆ(0.017mg/10g)
- ごはん(0.015mg/150g)×2回
- オクラ(0.014mg/16g≒3分の4本)×3回
- 米粉パン(0.013mg/52.5g)
- 大豆水煮(0.01mg/16g)
- 里芋(0.01mg/50g)×2回
- 小松菜(0.01mg/20g)×2回
- にんじん(0.02mg/33g)
- ほか(一食当たりの摂取量が0.01mg未満のものは省略)
一日の摂取量:約0.9mg以上
摂取難易度:★★★★★
続いてはビタミンB2。発育ビタミンとも呼ばれる、脂質の代謝を促進するビタミンです。こちらもB1同様突出して多く含む食材というものがなく、やはりバランスよく食べて摂る必要があります。そしてこちら、見ての通り現状では不足しているので、改善の必要があります。一応ブロッコリーやアーモンドを摂る量を増やす、などといった方法が一番現実的な気がしますね。それにしてもここまで描いた段階でブロッコリーの栄養素カバー範囲非常に広いですね。タンパク質や食物繊維まで豊富だし、多少高くなってもこれなら死守したくはなりますね。自家栽培始めたら真っ先に作るべき野菜No.1な気がしてきました。
ビタミンB6
- 四捨五入して0.1mg含有の食材
- パプリカ(30g)
- 納豆(40g)×2回
- 木綿豆腐(2分の1丁)
- ブロッコリー(65g)
- トマト(100g)
- 里芋(50g)×2回
- ひよこ豆(乾燥16g)
- 豆乳(100ml)
- ゴールドキウイ(40g)
- 葉ネギ(25g×2回)
- ごはん(150g×2回)
一日の摂取量:約1.3mg
摂取難易度:★★★★☆
続いてはビタミンB6。アミノ酸の代謝促進、皮膚の健康維持に欠かせない栄養素です。こちらも他のビタミンB群同様、突出して多く含む食材は少ないので、まんべんなくとっていく必要があります。わたしが摂っているもの以外だと、バナナも1本あたり約0.76mg含まれているので、朝にバナナを食べるのが無理なく摂取できるメソッドとしては良いのかもしれません。とはいえヴィーガニズム視点で見るとバナナは、植物性食材だからオッケー、というわけでもなく、生産国における労働問題や、栽培における生態系の破壊や水資源の消費といった問題がないわけではないので、それらの問題をクリアしているかどうかを、トレーサビリティによって生産毛色を確認したり、有機JAS認証などによって環境負荷の少ない方法で栽培されたものかどうかを確認したうえでの購入を検討する必要があります。これはコーヒーやココナッツ、綿花も同じですね。
ビタミンB12
続いてのビタミンB12は、おそらくヴィーガンにおいて最も摂取が難しい栄養素でしょう。理由は単純で、ビタミンD以上に摂取可能な食材に乏しいからです。具体的にビタミンB12が摂取できる植物性食材は以下の通りです。
- 海苔(1.7mg/3g≒1枚)
以上!
いや、冗談ではなくて本当にこれくらいしかありません。しょうゆとか酢とかにもありますが、本当にごく僅かなので足しになるかどうかってレベルです。ビタミンDすら2種類あったのにこっちはたった1種しかない。ちなみに海苔に含まれているのは、海苔に付着する水棲プランクトンに含まれているものだそうです。
そして当然これだけでは足りません。一応他にビタミンB12を含むものとしては、最近スーパーフードとして注目されている、ニュートリショナルイーストがあります。ヴィーガンがチーズの風味を再現するのによく使われるあれですね。それ以外だとサプリメントしかありませんが、そのサプリメントも何から抽出しているかを確認する必要があります。ビタミンB群はヴィーガンにとっては意識して摂取しないといけない代物ですが、その中でも意識しないとまず不足するビタミンB12は鬼門中の鬼門ですね。
ビタミンC
- ゴールドキウイ(56mg/40g≒2分の1個)
- パプリカ(51mg/30g)
- ブロッコリー(45.3mg/65g)
- トマト(15mg/100g≒2分の1個)
- 葉ネギ(8mg/25g≒1本)×2回
- 小松菜(3.6mg/20g)×2回
- 白菜(3.5mg/50g≒2分の1枚)×2回
- 里芋(2.5mg/50g)×2回
- ほか
一日の摂取量;約202.5mg以上
摂取難易度:★★☆☆☆
お次はビタミンC。鉄と併せてコラーゲン精製には欠かせない栄養素。見ての通り、ゴールドキウイがビタミンC摂取においては他の追随を許さないパフォーマンスを誇ります。なんせ1個摂取すれば一日分のビタミンCが摂取出来ますからね。他にはパプリカやブロッコリー、トマトといった緑黄色野菜に豊富ですね。しかしビタミンCは熱に弱いので、生食か食べる直前にゆでて食べる、といった工夫が必要です。パプリカにおいては熱することで摂取効率の上がるビタミンAも豊富なので生食用とマリネなどの炒め物用といった感じに調理方法を使い分けるのもいいかもしれませんね。小松菜や白菜の葉部分も、味噌汁にする際に本当にさっとゆでてすぐに食すれば、ビタミンCもある程度は摂れるのでいいかもしれません。
ナイアシン
- 木綿豆腐(3.3mg/2分の1丁)
- 納豆(1.8mg/40g≒1パック)×2回
- 豆乳(1.4mg/100ml)
- オートミール(1.4mg/30g)
- ごはん(1.2mg/150g)×2回
- トマト(0.8mg/100g≒2分の1個)
- 米粉パン(0.9mg/52.5g)
- まいたけ(2.5mg/50g)
- アーモンド(0.7mg/10g)
- ほか
一日の摂取量:約15.2mg以上
摂取難易度:★☆☆☆☆
次はビタミンB群の1種、ナイアシン。ナイアシンは厚生労働省のデータベース上ではナイアシン当量を参考にするのが良いそうです。血行を良くし、脳神経の働きを助けるのがナイアシン。こちらはミネラルの宝庫たる豆腐や納豆といった発酵食品に多く含まれています、また、舞茸にも豊富で、基本的に豆、穀類からも多く摂れるので、他のビタミンに比べるとあまり意識しなくても必要量を摂取できているものになります。
葉酸
- ブロッコリー(86.5㎍/65g)
- 納豆(52㎍/40g≒1パック)×2回
- ひよこ豆(38.7㎍/乾燥16g)
- 豆乳(28㎍/100ml)
- 葉ネギ(25㎍/25g≒1本)×2回
- ほか
一日の摂取量:約307.2㎍以上
摂取難易度:★☆☆☆☆
続いては葉酸。貧血予防や免疫力増進など健康維持には欠かせないビタミンB群のひとつ。こちらもブロッコリー、納豆というおなじみのスーパーフードでほとんど賄えます。葉ネギにも1本あたりに多く含まれていますね。ひよこ豆にも豊富なので、サラダやみそ汁にちょっと添える程度でも補給できるのも嬉しいところです。
ちなみに推奨量200mgを大きく上回っていますが、水溶性ビタミンは必要量を超えた分に関しては全て尿となって排出されるため、過剰摂取のリスクはないに等しいです。結果的に無駄になってはいるので適量にするに越したことはありませんが。
パントテン酸
- 納豆(1.5mg/40g≒1パック)×2回
- ブロッコリー(0.53mg/65g)
- オートミール(0.39mg/30g)
- ごはん(0.38mg/150g)×2回
- 豆乳(0.28mg/100ml)
- 里芋(0.2mg/50g)×2回
- トマト(0.17mg/100g≒2分の1個)
- ひよこ豆(0.17mg/乾燥16g)
- ゴールドキウイ(0.1mg/40g)
- 白菜(0.09mg/50g≒2分の1枚)×2回
- 米粉パン(0.1mg/52.5g)
- ほか
一日の摂取量:約6.08mg以上
摂取難易度:★★☆☆☆
お次はパントテン酸。HDLを増やしたり、糖質、脂質の分解したりと健康には欠かせないビタミンB群の1種。こちらも上位に来ているのは納豆、ブロッコリー。この2つがカバーする範囲の広さは改めてすさまじいものがありますね。納豆はモリブデンやビタミンKの過剰摂取リスクもありますがブロッコリーはそれすらない優秀さ。とはいえ、パントテン酸に関してはそれだけだと目安量に達しないので、他の食材からもまんべんなくとる必要があります。オートミールや悟飯といった穀物にも比較的多めに入っているので、納豆ご飯の優秀さが光りますね。ご飯の糖質の分解を促進することでエネルギー効率も高まりますし。他には里芋やひよこ豆などが見えているところからも、パントテン酸は野菜よりも豆類、穀類、イモ類といった炭水化物やたんぱく質を多く含む食材に多く含まれている傾向があるようですね。
ビオチン
- 納豆(7.3㎍/40g≒1パック)×2回
- 木綿豆腐(7.2㎍/2分の1丁)
- オートミール(6.6㎍/30g)
- ブロッコリー(5.1㎍/65g)
- 豆乳(3.8㎍/100ml)
- ひよこ豆(3.1㎍/乾燥16g)
- 豆味噌(2.6㎍/15g)×2回
- トマト(2.3㎍/100g≒2分の1個)
- 里芋(1.4㎍/50g)×2回
- ほか
一日の摂取量:約50.7㎍以上
摂取難易度:★★☆☆☆
最後はビオチン。皮膚の健康時、白髪や抜け毛の防止に働くビタミンB群の1種。こちらも多く含むのは野菜以上に豆類が際立ちますね。豆腐、納豆、豆乳、ひよこ豆、豆味噌とおなじみの豆製品が多く並びます。オートミールやブロッコリーのような多様な栄養素をカバーできる食材にも多く含まれておりますね。ソイプロテインが美容志向の人に需要が高いのも、こういった肌や紙の健康に貢献できる栄養素を大豆製品が多く含んでいるから、というのも大きそうです。
まとめ
以上、3つの記事にわたって、ヴィーガンである自分の食生活を通して、各種必須栄養素をどう摂取しているか、について紹介してまいりました。
結論を申し上げると、すべてを必要量摂れているわけではありませんでした。特にビタミンB12は明確に不足しているし、鉄やビタミンB2も怪しい部分はあります。
それらを意識的に補うことは確かに必要です。逆にわたしもこのように文字起こししてみて、自分に足りない栄養素を認識することができました。ニュートリショナルイーストを食卓に加えて新たなメニューを考えてみる、ブロッコリーやアーモンドを多く摂ってみる、など。そういった改善策を考えていくことで、きっと食生活はもっと楽しく、そして健康的になっていくものだと思います。
そして納豆におけるモリブデンやビタミンK、昆布だしにおけるヨウ素といった過剰摂取リスクのある栄養素があるのも興味深かったです。だしを昆布単品ではなく、椎茸や野菜との合わせだしにしてみたり、といった発想の転換も必要かもしれないなと思いました。
それを差し引いて総括してみると、やはりブロッコリー、豆腐、納豆の優秀さが際立ちましたね。ビタミンにおいてのブロッコリーと納豆の登壇率の高さは圧巻でした。逆に出過ぎてこれらはこれらで一体どれだけの栄養素を包含しているのかをまとめて見ても面白い気がしてきました。
とりあえずヴィーガンとしての栄養については、
基本的には不足するということはない。ただし鉄、ビタミンB群は意識する必要あり。
昆布だしや納豆といった特定の栄養素を過剰摂取するものもある。
ブロッコリー、豆腐は非常に優秀。ただし色々な食材からまんべんなくとってそのポテンシャルは活きる。
といった形に結論付けられるかな、と思いました。
以上、ヴィーガンとしての栄養管理について共有致しました。
この記事が少しでもヴィーガンについて興味がある方に何かしら参考になるものがあればうれしいです。